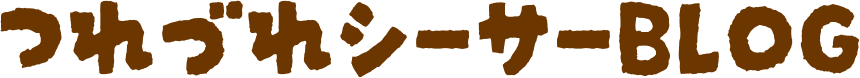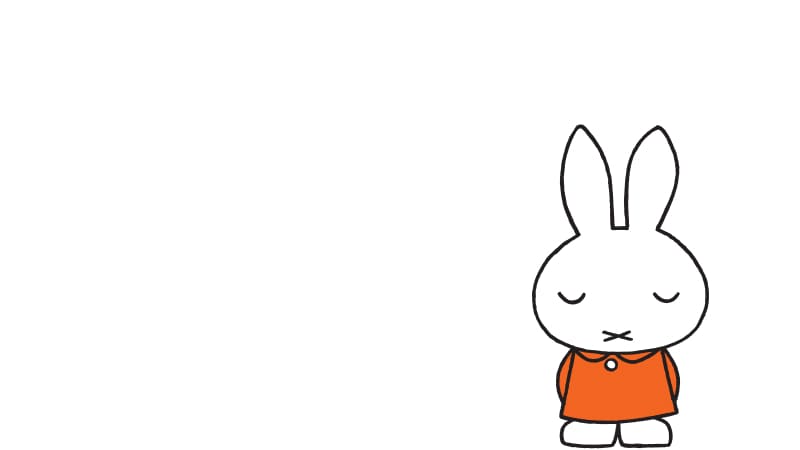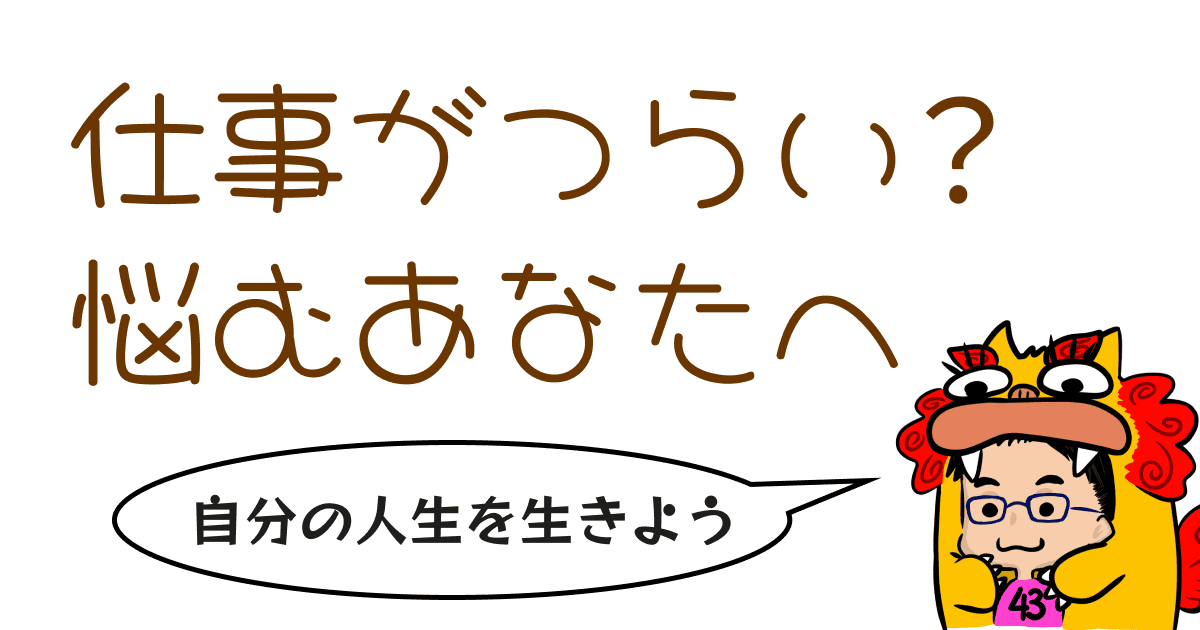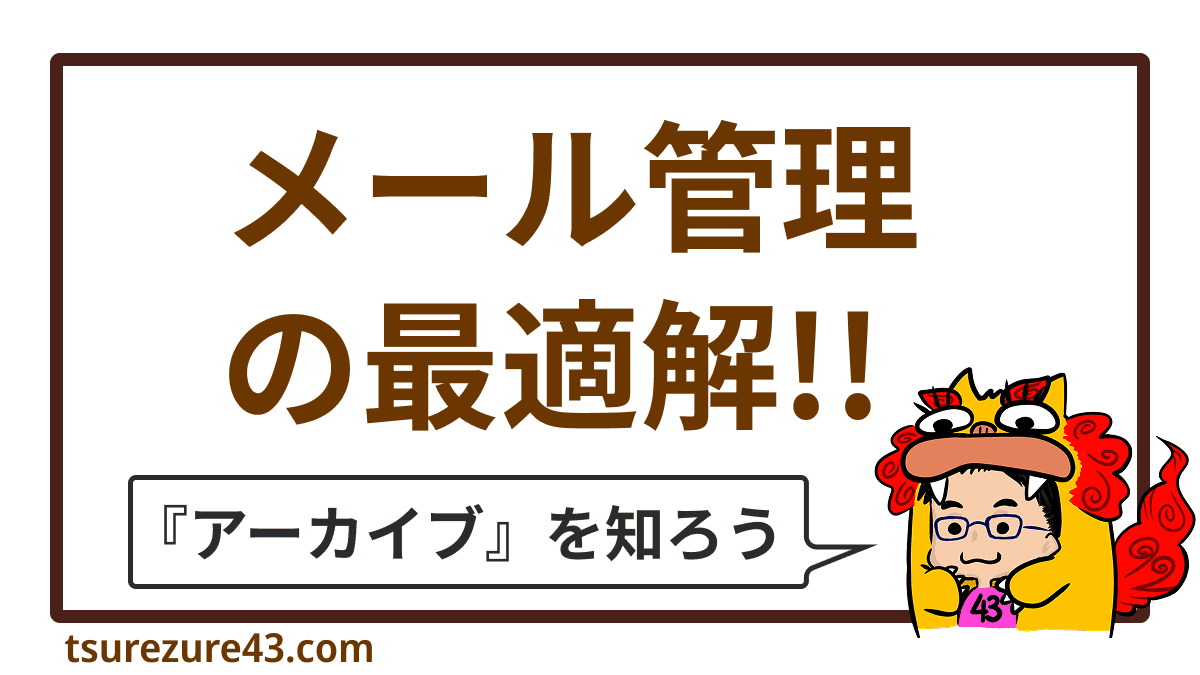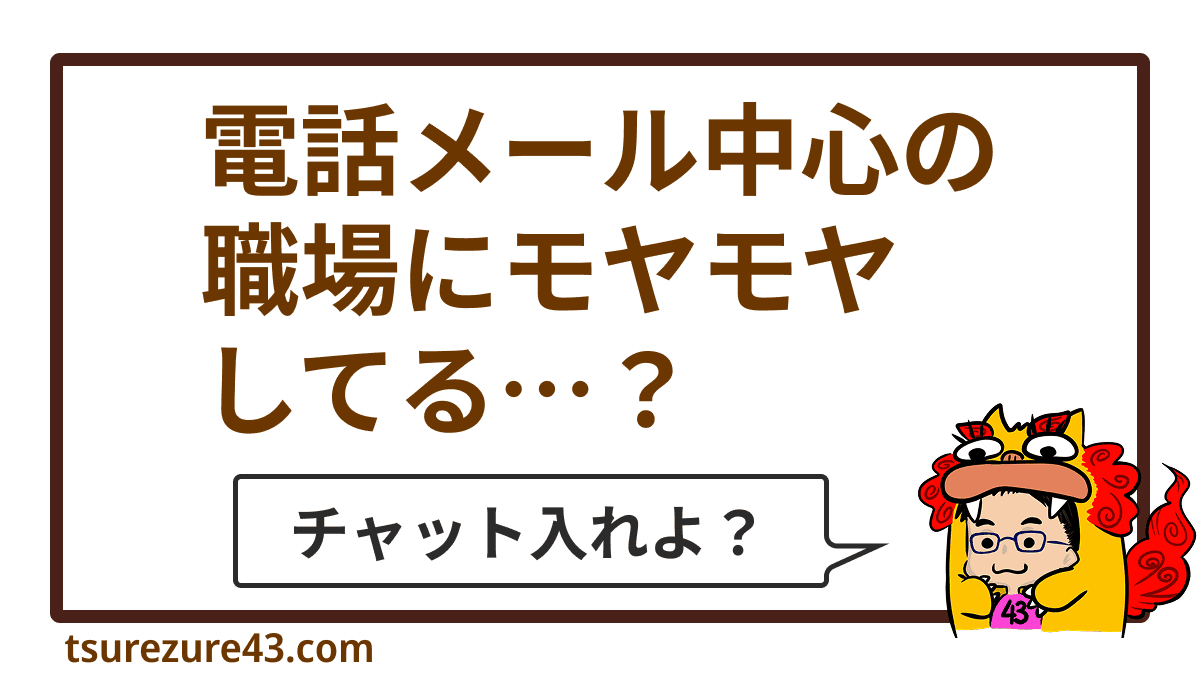副業禁止は違法?就業規則と法律の考え方|会社バレ対策とうまくやるコツ


会社が副業を禁止している、だと……??
「副業に興味があるけど…」
「会社の就業規則でダメ」
「税金でバレる?」
「バレたらどうなるの??」
あなたはきっと、副業に興味があってもなかなか始めることができない。
そんな状況だと思います。
この記事の目的は、その不安をグッと軽くすること。
「うちの会社は副業できない…」
そのマインドグロック、壊します!
正しい知識を身につければ、勇気を持って副業をスタートできます。
以前、こんな記事を書きました。
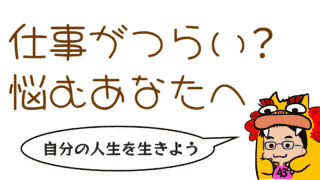
今回は、その続編みたいなお話。
ただただ会社の言いなりにならず、あなたの人生はあなたが選び取ってほしい!
そんな想いで、書きました。
結論:知識武装して、ビビらず副業しよう!
「会社が副業を禁止しているから……」
そう言って、チャンスを逃してしまう人は本当に多いように感じます。
でもね。ここで声を大にして言いたい。
それ、バカ正直に従う必要はありません!
もちろん、会社に迷惑をかけたり、本業をおろそかにしたりするのはNGです!!
でも、業務時間外の“あなたの人生”まで、会社に差し出す必要はない。
大切なのは、
- 正しい知識を持つこと
- 正しく行動すること
- 一歩を踏み出すこと
多くの不安は、知識不足から生まれます。
会社の「副業禁止規定」にビビるのではなく、事実を知って行動すれば大丈夫。
やりたい気持ちがあるなら、まずは小さく始めてみましょう。
その一歩が、きっと未来を大きく変えます。
実は「副業禁止」はアウト。理由と考え方
就業規則より、法律が強い

日本の法律、憲法22条では「職業選択の自由」を定めています。
実は「副業」も、この「職業選択の自由」に含まれます。
ここで考えるのが、法律と就業規則、どっちが優先されるの…?という疑問。
結論はシンプル。
法律>就業規則 です。
就業規則が、法律を超えることはありません。
あってはならないのです……。
そのため、就業規則に違反して副業したとしても、法的な罰則をうけることはありません。
さらに、副業だけを理由に「懲戒処分」や「減給」といった処分を、会社が社員に下すのも難しいのが現状です。
国も副業を推奨している

「厚生労働省」って、あるじゃないですか。
ちゃんとした、国の機関ですよね。
厚生労働省が、「モデル就業規則」ってのを発表しています。
いろんな会社の就業規則の見本となるのがこの、「モデル就業規則」。
2018年、厚生労働省はモデル就業規則から副業禁止に該当する内容を削除しました。
これの意味するところは、「副業禁止はもう古いよ!」ということ。
さらにさらに厚生労働省は、副業・兼業の促進に関するガイドラインなるものを発表。
ガイドラインのざっくりとした内容としては、
という感じ。
「副業容認について、ちゃんと情報開示しなさいよ!」と、国も言っているわけです。
それなのに、情報開示が一切されていない会社は……
と、勘ぐってしまうのは僕だけでしょうか??
「終身雇用」や「年功序列」が崩壊していると国も言及する現代、個々人の自助努力が求められる時代です。
「公務員」は別ルール
会社の就業規則よりも、法律が上。
という話をしました。
一般の会社員であれば、副業が法律に抵触することはないので怖くはないのですが。
一方、「公務員」については、法律で副業が禁止されています。
つまり、公務員が許可なく副業した場合は、ダイレクトに法律違反。
とはいえ「公務員だから副業はあきらめる…」という判断は、ちょっとまってください。
ここでまた、国の機関に登場してもらいましょう。
お次は「総務省」です。

2025年6月、総務省は以下の通達を公表しました。
【総務省 通知・通達】
営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について
地方公務員の兼業については、職員による自律的なキャリア形成、自己実現のニー
ズの高まりや、高齢化、人口減少など社会情勢の変化を背景として、兼業を希望する
職員が兼業できる環境を整備することが各地方公共団体に求められています。
冒頭から、なんだかオカタ〜イ、ムズカシイ文章が並んでいます…。
この通達、国がどんなメッセージを発しているのか、と〜ってもざっくりと言うと、
ということ。
公務員にも、会社員と同じように副業解禁の波がきている!
実際、ルール運用の見直しが進む自治体も増えてきています。
つまり、国は全面的に「副業」を推進しているというのが現代のトレンド。
「副業禁止」は時代錯誤。
一昔前までの常識は現代の非常識ということを、まずは認識してほしい。
ちょっと話を戻して。
では、公務員は今後の制度改正を待つしかないのか…?
答えはNOです。
考え方や正しい対応について、次の章で触れていきます。
税金と許可制。バレずにうまくやる基本
税金でバレる?仕組みを知れば問題なし!

結論、正しくやれば“税金バレ”は防げます。
ポイントは「住民税」。
稼ぎが増えると、住民税も増えるので。
会社に「住民税」の変化を知られない対策はシンプル。
これだけ!!
こうすることで、副業収入での税金は会社給与から天引きされることはないので、会社は社員の副業を感知することはできません。
そもそも、年間20万円の利益が出るまでは、住民税の確定申告は不要です。
思いっきってスモールスタートしましょう。
むしろ「自分でバラす」に要注意
税金バレ対策はほんとにシンプルなのですが……むしろそれ以上に注意するべきは、
です…。
- 業務時間中は副業しない
(業務に集中する) - 会社の看板で副業しない
- 会社の備品、情報で副業しない
- 同僚に自慢しない
「副業」以前に、倫理観や常識の話ですが、
会社の業務に真摯に取り組むことが、副業バレを防ぐ根本的な姿勢となります。
もちろん、副業バレを“絶対確実に100%”防ぐなんてことはできません。
でも、
- 住民税を「普通徴収」にする
- 自分でバラさない
(業務中は真面目に取り組む)
このポイントさえ抑えれば、現実的にはコントロールできるリスクです。
会社が「許可制」の場合。衝突しないお作法

ここでのお作法は、あくまで僕個人の意見としてお読みください。
m(_ _)m
もし会社が副業OKでも、「許可申請」が必要な場合。
「許可」は、わざわざ取らなくていいと思う。
(黙って副業しよ。ってこと)
そう思う理由を、お話しますね。
そもそも、業務時間外の社員の行動に、会社からの「許可」っていらなくないですか…?
じゃぁ例えば、もし業務時間外の「SNS」や「ゲーム」、もっといえば「休日の過ごし方」に会社の許可が必要ってなったら……?
( ゚д゚)ハァ? ザケンナッ!!
って、なりませんか…?
(口が悪くて失礼しました)
絶対おかしいし、無視しますよね。僕なら無視します。
副業もプライベートのことなので、黙ってやればいいと思う。
そして何より重要なのが、

繰り返します。
会社に副業してることを報告しても、なにひとつとしてメリットがないんです。
会社に「許可申請」したからっていって、勤務時間が短くなったり、業務量が少なくなったりするわけではありませんもんね。
それどころか――
こんなパターンを想像してみてください。
「残業お願いしたいんだけど…」
「明日の朝、早く来てくれる?」
「次の休日、出勤できるかな?」
「飲み会、参加するよね??」
これらの要求について、断われるものであればあなたは積極的に「NO」を突きつけます。
あなたはプライベートの「副業」のほうが、優先度が高いから。
もし、会社(上司や同僚)があなたの「副業」を知っていたら…?
「あの人は『副業』してるから…」
そう言われて、後ろ指を刺されるのがオチです。
ちょっと業務のパフォーマンスが落ちたり、ミスが増えちゃうタイミングもありますよね。
直接的に関係ないことでも、何かと「副業」に紐付けられてマイナスイメージとなることが予想されます。
言ってもメリットがなく、むしろデメリットしかないのであれば――
ただただ静かに、慎ましやかに副業しましょう。
「沈黙は金」ということわざもありますもんね。
公務員は?“無償で”家族のお手伝いをしよう
ここでの話は、“行間を読んで”いただきたい。
m(_ _)m
文章の文字で直接表現されていない書き手の真意、心情、または隠されたメッセージを汲み取ること。
公務員は、法律で「副業」が禁止されているというお話をしました。
その理由は、国民や住民のためにお仕事に従事する公務員は、営利を目的とした活動(つまり「副業」)をするのがNGだから。
――なるほど。
公務員個人が営利を目的としなければ、それは「副業」には該当しないわけです。
例えば、家族がなにかしらの事業をしていて、それを“無償で”お手伝いするだけであれば、それは「副業」にはなりません。
お手伝いをしてくれる人がいれば、家庭内での収入は増えますよね?
家庭内での支え合い、とても心温まりますね。
(*^ω^*)
悲痛な叫びと切望を聞いてくれ
これはあくまで、僕が感じたことなんだけど…
「このご時世、かたくなに副業禁止している会社って……ダサくね?」
突然のディス。
会社にも言い分はあるのかもしれない。
でも――
納得できる説明を、少なくとも僕は聞いたことが無い。
よく出てくる根拠は、だいたいこうだ。
- 職務専念義務
「時間内は業務に集中してね」 - 守秘義務
「業務上の秘密は守ってね」 - 競業避止義務
「会社のライバルになることはしないでね」 - 服務規律
「会社の信頼やブランドを損なわないでね」
就業規則で、よく目にするちょっとムズカシイ文言。
どれも大切。異論はない。
でもこれは、倫理や常識の話であって――
「副業」以前の問題じゃね?
「副業を一律無条件に禁止する理由」には、ならんやろ。
ソレが理由になるならさ…
寝不足で出社する社員の「夜ふかし」を禁止しなよ。
職務専念義務違反だよ?
社名を出しながら愚痴っている「飲み会」を禁止にしなよ。
守秘義務違反、服務規律違反だよ??
でも、わざわざ「夜ふかし」や「飲み会」を、就業規則で禁止にはしないよね?
常識の話だから。
なのに「副業」は丸ごとNG、はやっぱり不自然だと思う。
これはあくまで、僕が感じたことなんだけれど、
正当な理由(説明)なく、ただただ一律無条件に副業を禁止している会社って――
自社に自信が無いんだと思う。
自信がないから、社員が外の世界(「副業」で他の仕事)を知って、離れていく(離職する)のが怖いんじゃないかな。
だから、理由なく社員の私生活を制限するのでは?
と、まぁ……過激な個人的感想なのだが、それでもやっぱり僕としては、
- 時代の変化に適応しない
- 説明責任を果たさない
- 社員と向き合わない
- 社員の人生を制限する
そんな会社を見ると、どうしても悲しい気持ちになるのだ。
社員を信じて、ともに成長する会社であってほしい
気を取り直して、ここからは前向きなお話を。
「副業」は社員だけでなく、会社にもプラスの影響があると思う。
- 経験が増える
(現場での判断が速くなる) - 知識が広がる
(提案の幅が出る) - スキルが磨かれる
(生産性が上がる)
業務外で磨いた力は、本業にも還元される。
業務外でも自分の経験やスキルを磨こうとする社員はきっと魅力的で、会社を良い方向へ導いてくれる。
――理想はこの循環。
- 社員を信頼する
- 社員に選ばれる
- 社員が能力を還元する
- 会社全体が成長する
そんな好循環を、実現してほしい。
社員を信じ、社員に選ばれ、社員とともに成長する。
そんな会社が増えてほしい。
この記事が、誰かの“不都合な真実”ではなく、今後を考える前向きなきっかけになりますように。
まとめ
ぜひ観てほしい動画
「副業始めたいけど、まだ少し不安…」
「何から手をつけるべき…?」
そんなあなたに、ぜひ観てほしい動画を2つ紹介させてください。
「まだ少し不安…」、そんなあなたへ。
※この記事も、この動画を参考にしています。
σ( ̄∇ ̄; )
「何から手をつけるべき…?」と考えているあなたへ。
こちらはタイトルが「おすすめしない副業」とありますが、大きく方向性を間違わないためにも、観てほしい動画です。
関連動画に、「おすすめ副業9選」といった別動画リンクもあり。
続けて観るのがオススメです。
多くの不安は、知識不足から生まれます。
知識をアップデートして、不安を解消しましょう!
最後に
最後まで読んでくれて、ありがとうございました。
もし今の働き方にモヤモヤがあるなら、小さく始めてみませんか?
結論はシンプル。
- 事実を把握する
(法律と会社の線引きを知る) - 正しく行動する
(税金の知識・黙ってやる) - 小さく始める
(気になることから始めてみる)
まだまだ不安なことはあるかもしれません。
でも、一歩踏み出せば違った世界が見えてきます。
完璧じゃなくていいんです。
失敗しても大丈夫。
学びに変えれば、それは前進です。
- 会社の規則に縛られる現状
- 自分の意思で動き始める未来
選べるのは、いつだってあなた。
だって、あなたの人生だから。
静かに、賢く、うまくやろう。
この記事が小さな一歩を踏み出すきっかけになれたら、うれしいです。
一歩踏み出すあなたを、心から応援しています。
それじゃぁ、またね!