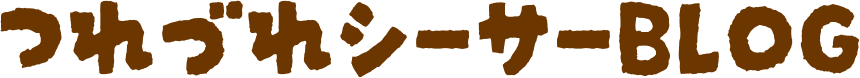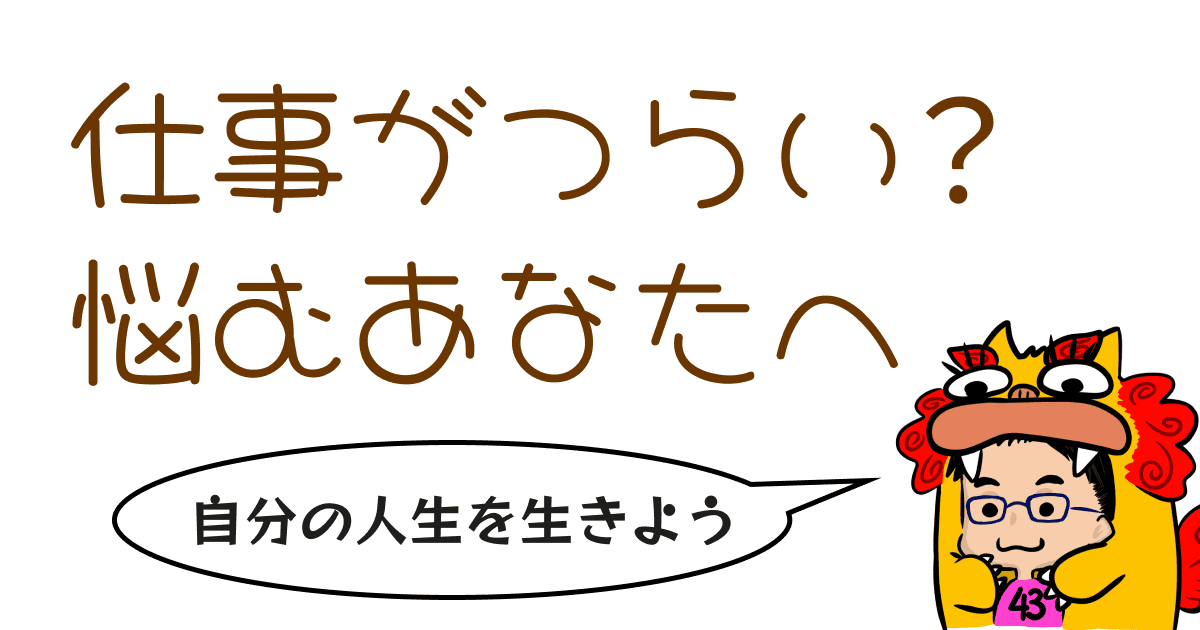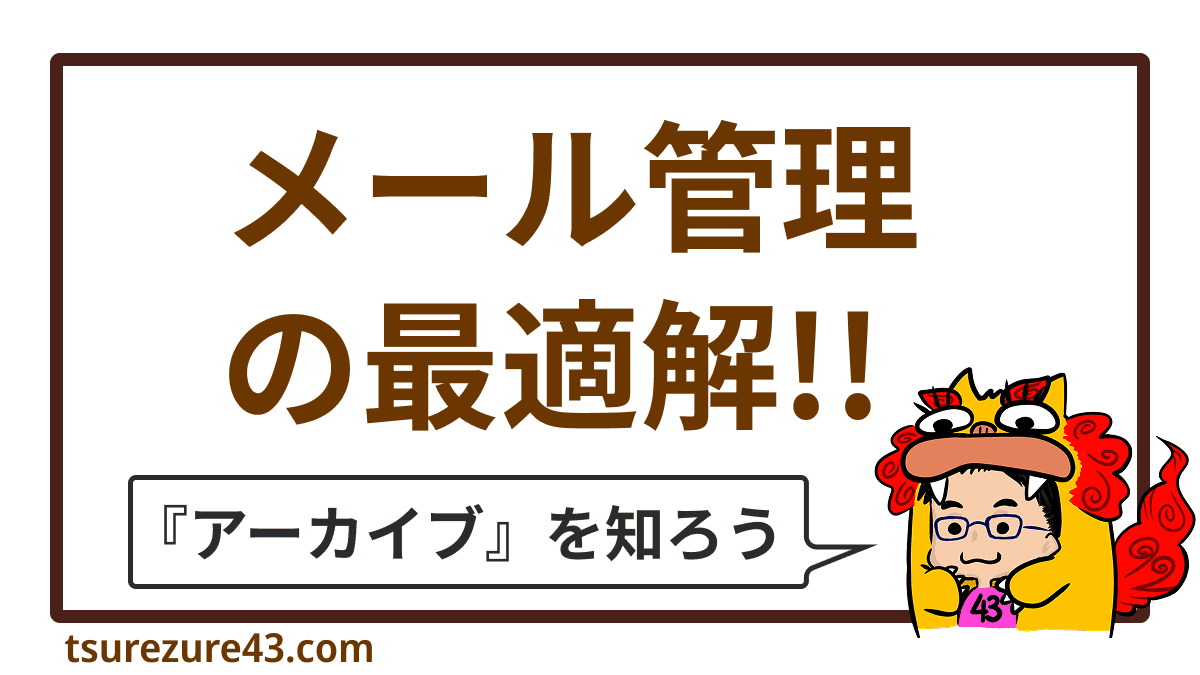電話とメールだけの職場にモヤモヤしてる?チャット導入で変わる働き方の話
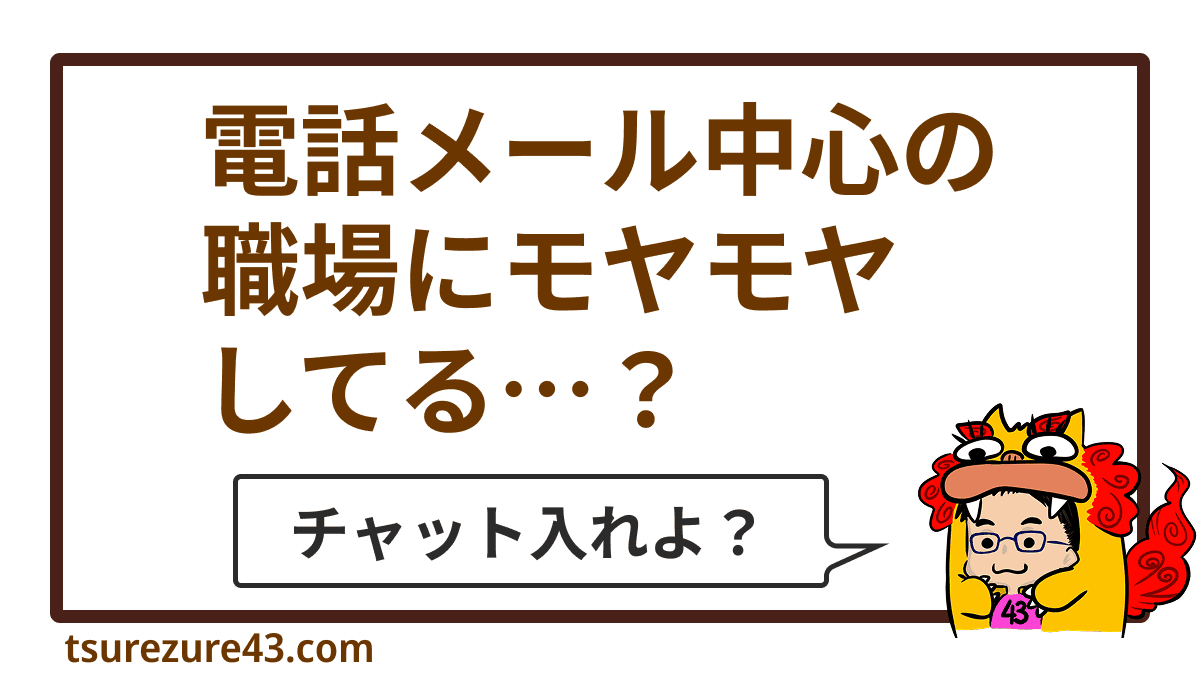
- 業務での電話が苦手
- メールもめんどくさい
- そもそもメール慣れてない…
- 忙しい上司に直接話しかけるのも気が引ける
- なんでチャット使わないの…?
──そんなモヤモヤ、抱えてませんか?
新しい会社に入社して、ちょっと仕事に慣れてきたころ。
ふと気づくと、いろんな“やりにくさ”が見えてきますよね。
僕が新入社員で入った会社も、
- 電話
- メール
- 口頭(直接話しかける)
だけがコミュニケーションの手段でした。
ザ・古風。
「なぜチャットツールを使わないんだ…!?」
当時はそう思いつつも、気づけば自分も慣れていく日々。
でもその後、2回の転職を経験し、
チャットツールのある職場とない職場では、働きやすさに天と地の差があることを思い知らされました。
この記事では、
あなたのモヤモヤの正体と、
それを解決できる具体的な方法をお伝えします。
「…若手の自分が言っても意味ないよ」って??
いえいえ、大丈夫。
この記事は、そんなあなたのために書いています。
どうか最後までお付き合いください!

若手社員の正直な気持ちを代弁したり、会社をより良くするヒント、しっかりお届けします!
この記事で伝えたいこと
この記事を読んでほしいひと
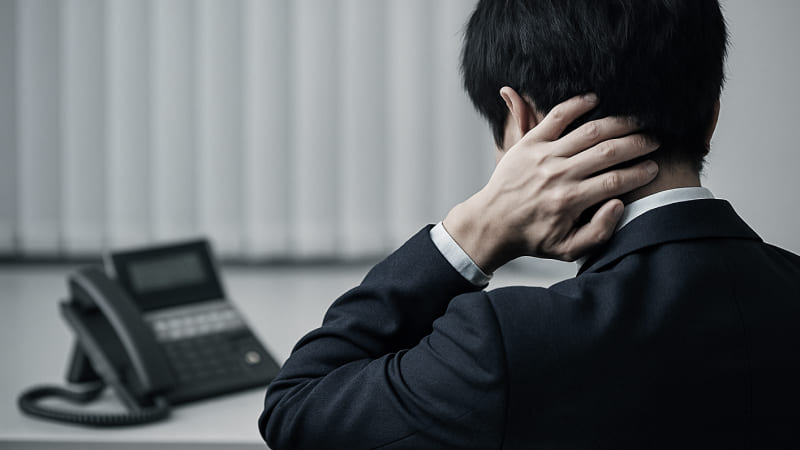
この記事は、こんな方に向けて書いています。
- ちょっとモヤモヤを抱えている若手のあなた
(「チャットツール入れてほしいな」と考えているあなた!) - その上司や決裁権をもつ方
(「口頭、メールで十分でしょ!」と思っているあなたにもぜひ!!)
つまり、この記事で目指しているのは──
お悩みを抱えた若手社員と、決定権をもつ上司の“橋渡し”です。
お互いの「言いづらさ」や「気づけなさ」を、やさしく繋ぎたい。
社内のコミュニケーションが、もっとスムーズで、もっとラクになる。
そんな未来のための第一歩になればうれしいです!

チャットの話なんだけど、実は“人間関係の話”でもあるのです
先に結論

まず、あなたに伝えたい結論はこれです。
……って、そんなの上の人が決めることだし、
自分が言っても何も変わらないって思っちゃいますよね?
でも大丈夫。
この記事を読んでくれたあなたが、“きっかけ”になることはできます!
実はチャットツールは、
- 気軽なホウレンソウができる
- コミュニケーションのハードルが下がる
- 上司との距離が少し縮まる
といったあなたの「やりにくさ」を和らげてくれるツールです。
しかもそれだけじゃない!
あなたの上司にとっても、うれしいことに…
- 心理面(組織文化・人材育成)
- 実務面(業務効率)
- 経営面(コストリターン・意思決定)
まで、幅広い課題にも効果あり!
信じられないかもしれませんが、実際に使ってみたら「もっと早く導入すれば…!」と感じるはず!!
なのでもう一度、結論。
チャットツール、入れよう!

“業務効率化”って聞くと難しく感じるかもですが、
実は“働きやすくなる”ってことなんです
なぜチャットツールが必要なのか?
「電話・メール中心」による若手のストレス

まずお伝えしたいのは、
ということ。
社内だけでなく、社外のお客様や協力会社とのやりとりもある中で、
「それでも慣れてもらわなきゃ困るよ…」
という上司の、あなたの気持ちもわかります。
実際、僕もそう思っていました。
でもあるとき、研修担当として新人と向き合ったとき、その考えがガラッと変わった出来事がありました。
電話が苦手な新入社員に理由を聞いたところ、返ってきた答えは──
電話をかけるのが“怖い”んです
知らない人からの電話に出るのも、“怖い”んです
「怖い…??」
正直、最初は「この子の性格的な問題かな?」と軽く考えてました。
でも、同じように感じてる新人が他にも。
・・・・・・・そこで、あることに気づいてハッとします──
そんな軽い問題では無い
と。
──────
昔は、友だちの家に固定電話でかけて、
「誰が出るかな…」とドキドキしながら、こう言ってましたよね。
「〇〇くんいますか〜?」
──────
でもスマホ世代は、ソレを経験していないんです。
電話というツールが、彼らにとっては“馴染みのないもの”なんです。
つまり、どういうことか?
電話が苦手 = 甘えではなく、
“文化の違い”
だったのです!!
この“文化の違い”を、逆の立場で考えるとどうでしょうか?
たとえばチャットに慣れていないあなた(上司)が、会社からいきなり
「今後は口頭・電話NG。全部チャットで」
と言われたら…?
想像できますか……??
やっぱりストレスを感じますよね。
それと同じように、若手社員にとって電話やメールは、
日常的にストレスがかかるツール
なんです。
もちろん、ビジネスの現場では慣れる努力も必要です。
でも、「相手の苦手を尊重すること」も大事なコミュニケーションの第一歩ではないでしょうか?
そしてその“歩み寄り”の一手が、チャットツールの導入なんです。

1990年生まれの僕は、どちらの気持ちもとてもよくわかるのです…
若手が育たない・辞めていくリスクも

いろんな会社で働いてきましたが、辞めていく若手社員を何人も見てきました。
もちろん、単に会社との相性が合わなかったというケースもあると思います。
でも、やっぱり多かったのは──
- 人間関係の悩み
- コミュニケーション不足
- 小さなストレスの積み重ね
でした。
パワハラとか、明確なトラブルがあったわけじゃない。
でも、なんとなく話しづらい。
伝わってるか不安。
そんな「ちょっとずつの我慢」が、気づけば限界を超えてしまう。
いわば、“静かな退職”の理由です。
この記事を読んでくださっている方は、もしかしたら似たようなモヤモヤを抱えているかもしれません。
もしそうなら──
できるだけ早く、手を打ったほうがいいです。
なにか劇的な解決策じゃなくても、
「チャットで気軽に話せる環境がある」だけで、だいぶラクになる。
くどいですが、結論。
チャットツール、入れよう!!

“どうにかする”一歩を踏み出しましょう!
チャット導入で変わること
スピード感・共有のしやすさ
まず、何より変わるのが、
電話だと、「連絡したいけど、つながらない…」ってこと、ありますよね。
その上メールだと…
・宛名を入力して
・件名を書いて
・挨拶文を入れて
・要件をまとめて……
・最後に、
「よろしくお願いいたします」
( ゚д゚) おぉ〜っとここですでに10分が経過したぁー!!
でもチャットなら、
これだけ。
わずか30秒で完了です。
そして、チャットには便利な“スレッド”や“グループ”機能があります。
情報が流れず、テーマごとにやり取りがまとまるので、
「えっと、、、あの話どこ行った?」
が激減します!

“探し物の時間”が減って業務効率もUP!
ホウレンソウが自然と増える

正直に言います。
僕が電話・メール・口頭文化の古風な職場にいたときは「ホウレンソウ、めんど…」って思ってました。
先輩、上司になにか伝えたいときも、
「今、忙しそうだな…」
「メールで送ったら怒られるかな…」
「直接言うのもタイミングむずい…」
コミュニケーションのハードルが、高い!
まぁ、話しかけにくい雰囲気をかもしだしている先輩・上司にも問題はありますが……
(この話は、また別の記事でじっくり書きますね。)
結果、言わない(報告・相談しない)
→ 詰む。
でもチャットなら、「今すぐ見てくれなくても大丈夫」前提で送れます。
- 自分のタイミングで伝えられる
- 相手のタイミングで見てもらえる
- 話題が流れない(ログが残る)
- 場合によっては、写真を送れば言葉すら不要に!!
だから、気軽に伝える文化ができるんです。

チャットの“話しやすい”は、職場の雰囲気を良くします!
心理的な負担を減らす
チャットの地味だけど最強な機能。
それが「スタンプ」
メールにスタンプは……
✉️ありません!!(残念)
でもチャットなら、
- ありがとう🙏
- 了解です🫡
- よろしく🙇♂️
って感じでスタンプだけで「伝わった感」が出せます!
気軽にレスポンスができるということは、若手社員側にも上司側にも、めっちゃありがたいですよね。

あ、見てくれたんだ!
ってわかるだけで、けっこう気持ちがラクになります。
そして、チャットツールによっては「既読」機能があるものも。
これも便利な機能ではありますが…
「既読=すぐ返信しなきゃ💦」
という風に、心理的な負担となってはいけません。
チーム内で、
- 既読=あくまで確認しただけ
(もっと言えば開いただけ) - 即返信やレスポンスは不要
- 返信が必要なら、そう伝える
といった感じで、チャットのルールを明確化しておくことが重要!
「お互いが安心できる手段」として、チャットを活用しましょう!!

チャットの便利機能やテキストコミュニケーションの“心得”は、また別の記事で書きま〜す
小さな変化が、大きなやりやすさを生む
チャットを入れたからと言って、いきなり業務が100倍ラクになる!なんて魔法ではありません。
でも、こうした“小さなやりとりの快適さ”が積み重なることで、
- 心の余裕ができる
- コミュニケーションが増える
- 職場の雰囲気が良くなる
- 結果、仕事の質が上がる
っていう、いい循環が生まれます。
だから、何度でも言います…
あなたの職場にも、必ず変化は起こせます!
チャットツール、入れよう!!!
スタートにベストなツール
おすすめはLINE WORKS
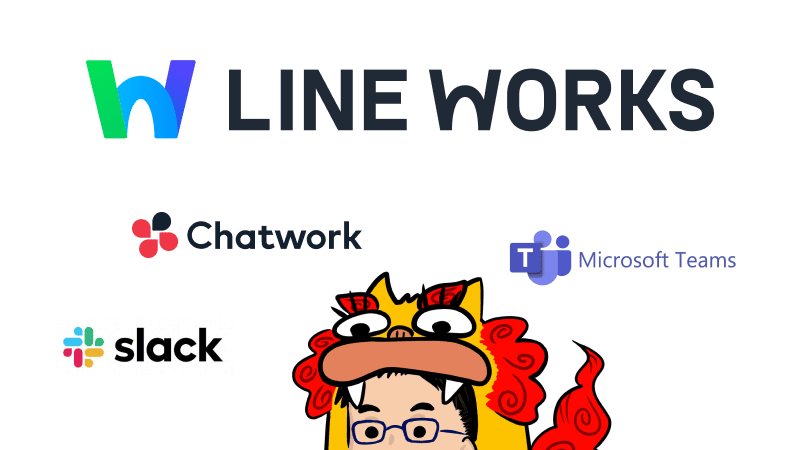
いろんなチャットツールを使ってきましたが、「最初の1歩」にいちばん向いてるのは……
です!
僕は現在、複数のツールを用途に合わせて使い分けています。
- 社内
→ LINE WORKS - クライアントA社
→ Chatwork - クライアントB社
→ Slack
みたいな感じ。
どのツールもそれぞれ良いところがあるんですが──
「まず社内で導入してみようかな?」というスタート段階では、
LINE WORKSが圧倒的におすすめ!
その理由を次でお伝えします!

いろんなツールを使っている僕だからこそ、自信をもってオススメできます!
なじみのあるUIだから、導入・教育コストが少ない
LINE WORKSのいちばんの強み、それは──
見た目も、操作感も、普段使ってるLINEとほぼ同じ。
つまり、
「新しくチャットツールを覚える…」
ではなく…
「LINEを“仕事モード”で使う感覚!」
で始められるのです!!
つまり、ITに詳しくない社員さんや、年齢層高めの方が多い職場でも、導入のハードルが低いということ。
「“これなら自分でもできそう”」って受け入れてもらいやすいのが最大のメリットです。

“教育コスト”がほとんどかかりません
無料でも十分に使える
(でも有料もコスパ◎)
そしてありがたいのが、無料プランでもかなり使えるという点。
- トーク(チャット)
- 音声・ビデオ通話
- スケジュール共有
- 掲示板・ToDo・アンケート機能
- データ(写真など)保存容量
- カスタマーサポート
などなど……
「え、これ無料でいいの?」と思うくらい、機能が充実してます。
でも…!!
特に、
- 部署ごとのアクセス権限の設定
- メンバーの管理・一括削除
- データ容量の拡張
など、“社内で本格導入したい”ときの土台がしっかり作れるんですよね。
最初は無料でお試し
→ 慣れたら有料へ
というステップを踏めるのも、LINE WORKSのいいところ。

管理やセキュリティー面を考慮すると、有料版の利用をオススメします!
他のチャットツールとの簡単な比較
(あくまで僕の主観)
もちろん、LINE WORKS以外のツールにもそれぞれ良さがあります!
- Slack
エンジニア・IT企業に人気。
連携や拡張性がすごい。
ちょっと専門的…。 - Chatwork
日本の中小企業に多く導入。
シンプルで見やすい。 - Teams
Microsoft連携が強い。
Office製品との親和性◎ - LINE WORKS
LINEにそっくり。
非IT層でも馴染みやすい。
僕はこの4つ、すべてガッツリ使ってきましたが──
もし「職場で最初に1つ導入してみようかな?」という段階なら、
やっぱりLINE WORKSがいちばん“とっつきやすい”と感じてます。
新しい取り組みを試してみるときは、

せっかく導入しても“誰も使ってくれない問題”は避けたいですよね
まとめ
チャットツールは働きやすさの“第一歩”
「電話もメールも、正直ちょっとしんどい…」
「なんでチャット使わないんだろう?」
そんなモヤモヤを抱えている若手社員のあなたへ。
そして、
「うちのやり方はこれで十分」
と感じている上司のあなたへ。
この記事では、チャットツールを導入することで生まれる“ちょっとした変化”をお伝えしてきました。
- スピード感がアップする
- 気軽なホウレンソウが増える
- 心のストレスが減る
- 職場の空気がちょっとだけやさしくなる
もちろん、チャットを入れたからって劇的にすべてが変わるわけじゃありません。
でも、「話しやすい」「伝えやすい」が当たり前になると、
その小さな変化が、いつのまにか“働きやすさ”につながっていくんです。
だからこそ、思いきって伝えたい。
「うちの会社にはまだ早いかな…」
「いきなり全員はちょっと…」
そんなときは、まずは一部の部署やチームで試してみるだけでもOK!
ちょっとずつ、少しずつでいいんです。
大事なのは、「変えたい」と思っている誰かが、
“最初のひと声”をあげること。
この記事が“最初のひと声”を届けるきっかけになればうれしいです。
この記事で紹介した LINE WORKS の詳細はコチラからどうぞ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
〜おまけ〜 次回予告?

もうチャットは使っているけど、プライベートのLINEだって……!??
セキュリティーや個人情報(顧客情報)保護の点で完全にアウトです。
もはや、職場のモラルが問われるレベルです。
「…そんなこと、上司に言えない」
「……さすがにプライベート混同はないけど、チャットどうこう以前に気軽に相談できない(上司が怖い)」
もしあなたが、職場(上司)に威圧感や恐怖を感じているのであれば、ココロが折れてしまう前に脱出(転職)してください。
【YouTube動画紹介】
※チャットの話ではありませんが、「心がしんどいな…」と感じている方に届いてほしい動画です。
会社の常識は、世間の非常識
あなたの人生、あなた自身を一番に大切にしてください。
それではまた!